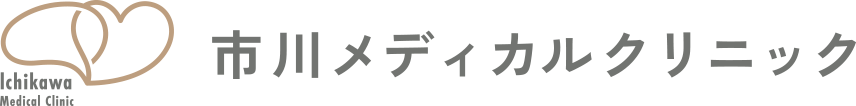- 躁うつ病(双極性障害)とは
- 躁うつ病(双極性障害)の原因
- 躁うつ病(双極性障害)の症状
- 躁うつ病(双極性障害)になりやすい人(傾向)
- 躁うつ病(双極性障害)の検査・診断方法
- 躁うつ病(双極性障害)の治療方法
- 躁うつ病(双極性障害)に関するよくある質問
躁うつ病(双極性障害)とは
躁うつ病(双極性障害)は、気分が異常に高まる「躁状態」と、極端に落ち込む「うつ状態」を繰り返す精神疾患です。この二つの状態が少なくとも1度ずつは現れ、患者様の生活に大きな影響を与えることがあります。躁状態では、爽快感を認めエネルギッシュで活発になり、感情や行動に抑制が効かずに過度な自信や衝動的な行動が見られることがあります。一方、うつ状態では、気力がなくなり、無気力感や絶望感が強くなるため、日常生活が困難になることもあります。適切な治療を行うことで、症状をコントロールし、安定した日常生活を送ることが可能です。
躁うつ病(双極性障害)の原因
躁うつ病(双極性障害)の原因は、複数の要因が複雑に絡み合うとされています。主な原因は、遺伝的要因、生物学的要因、環境要因の三つに分けられます。
遺伝的要因
家族に躁うつ病を発症している方がいる場合、発症リスクが高くなることが知られています。双極性障害は遺伝的要因が強く、特定の遺伝子が関与している可能性が指摘されています。ただし、遺伝だけで発症するわけではなく、他の要因と相互に影響し合うことが一般的です。
生物学的要因
脳内の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなど)の異常が躁うつ病に関連していると言われています。これらの物質は気分や感情の調整に関与しており、そのバランスが崩れると躁状態やうつ状態が引き起こされます。特に脳内の感情制御システムにおける不調が指摘されており、脳の特定の部位の活動や構造の異常が確認されています。
環境要因
ストレスフルな出来事や生活の変化が躁うつ病の発症や症状悪化の引き金となることがあります。例えば、仕事や人間関係の問題、家庭内のトラブル、重大な喪失体験(離婚や死別など)がきっかけとなり、発症することがあります。また、睡眠不足や生活習慣の乱れも症状を悪化させる要因となるため、日常生活のリズムを整えることが重要です。
躁うつ病(双極性障害)の症状
躁うつ病(双極性障害)の症状は、「躁状態」と「うつ状態」が現れるのが特徴ですが、一般的にはうつ状態の期間が長い場合が多くみられます。
躁状態の症状
- 異常なほどの爽快感や高揚感や多幸感
- 活動量やエネルギーの増加
- 異常に自信に満ちた自己評価(誇大妄想)
- 睡眠がほとんど必要なくなる
- 話が止まらず、思考が急速に進む(観念奔逸)
- 物事に対する注意が散漫になる
- 衝動的な行動(浪費、軽率な決断、無謀な行動など)
- 社交的、過度におしゃべりになる
- イライラしやすく、攻撃的な態度をとることもある
など
うつ状態の症状
- 長期的な気分の落ち込みや悲しみ
- エネルギーや意欲の著しい低下
- 楽しいと感じていたことへの興味や喜びの喪失
- 睡眠障害(不眠または過眠)
- 食欲の変化(増加または減少)
- 自責感や無価値感
- 集中力や決断力の低下
- 死についての考えや自殺念慮
- 身体的な疲労感や痛みの訴えが強くなることもある
など
躁うつ病(双極性障害)になりやすい人(傾向)
躁うつ病(双極性障害)になりやすい人(傾向)として、家族に罹患者がいる遺伝的要因のほか、ストレスの多い環境にいる、あるいはトラウマ体験、虐待を受けたことがあるなど環境的要因も考えられます。また、感受性の高い人や活動的でエネルギーが過剰に湧くタイプの方、脳内の神経伝達物質のバランスが乱れている方がなりやすいとされています。
躁うつ病(双極性障害)の検査・診断方法
躁うつ病(双極性障害)の検査・診断は、医師による問診や診察に基づき行います。診断の際には、DSM-5やICD-10などをもとに、他の精神疾患と鑑別を行います。また脳や身体に異常がないか確認するため、血液検査やCT検査など画像検査を行うこともあります。
躁うつ病(双極性障害)の治療方法
躁うつ病(双極性障害)の治療は、薬物療法と心理療法を組み合わせて行うのが一般的です。治療は患者様の症状に応じて調整し、長期的に安定した状態を維持することを目標とします。
薬物療法
薬物療法は、双極性障害の治療において中心的な役割を果たします。
気分安定薬(ムードスタビライザー)
リチウムやバルプロ酸ナトリウムなどが使用され、躁や抑うつの症状の急激な変動を防ぎ、気分の安定化を図ります。リチウムは双極性障害に最も効果的な薬の一つで、定期的な血中濃度の確認が必要です。
抗精神病薬
オランザピンやクエチアピンといった抗精神病薬は、特に躁状態の治療に用いられ、興奮や過活動を抑えます。これらの薬は、気分の変動を安定させるために併用されることもあります。
抗うつ薬
抑うつエピソードが強い場合には抗うつ薬が処方されることがありますが、躁転(躁状態への移行)のリスクがあるため、単独ではなく気分安定薬と併用することが一般的です。
心理療法
薬物療法と併行して、患者様が病気と向き合い、ストレスに対処するために心理療法が行われます。
認知行動療法(CBT)
認知行動療法は、患者様が自分の思考や行動パターンを認識し、それをポジティブに変えることを目指します。双極性障害においては、症状が現れる前兆を自覚する訓練や、生活リズムを整えるための技術が教えられます。
対人関係療法(IPT)
対人関係療法は、人間関係の問題がストレスとなり、気分に影響を与えることがあるため、患者様の対人関係の改善を目指します。双極性障害の患者様が、ストレスを軽減し、生活におけるバランスを取るための技術を習得することができます。
生活習慣の改善
双極性障害の治療では、規則正しい生活習慣が症状の安定に重要です。十分な睡眠、規則的な食事、適度な運動が推奨されます。特に睡眠不足は躁状態を誘発しやすいため、日々の睡眠時間を一定に保つことが大切です。
躁うつ病(双極性障害)に関するよくある質問
躁うつ病と双極性障害は同じですか?
躁うつ病と双極性障害は、同じ病気を指す異なる名称です。躁うつ病は、気分が異常に高揚する「躁状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」が現れることから名付けられました。一方、双極性障害は、より包括的な名称として用いられ、さまざまなタイプの気分エピソードを含むことができます。
双極性障害は、主に以下の3つのタイプに分類されます。
双極性障害 I型
このタイプでは、重度の躁状態(極端な高揚感や過剰なエネルギーを伴う)と重度のうつ状態(深い悲しみや無気力)が交互に現れます。躁状態は、患者様の生活に大きな影響を及ぼし、時には入院が必要なこともあります。
双極性障害 II型
このタイプでは、軽度の躁状態(軽躁)と重度のうつ状態を経験します。軽躁は、過剰な自信や活発さを伴いますが、重度の躁状態にまで至ることはありません。重度のうつ状態は、日常生活に深刻な支障をきたすことがあります。
サイクリック障害
このタイプは、軽躁状態と軽度のうつ状態が交互に現れますが、重度のエピソードはありません。これにより、症状は軽度であっても、患者様の日常生活に影響を及ぼすことがあります。
双極性障害は、遺伝的要因、環境要因、神経化学的要因が複雑に絡み合った結果とされており、正確な原因は未だに完全には解明されていません。治療には、薬物療法(気分安定薬や抗うつ薬)や心理療法が用いられ、症状の管理と再発予防が重要です。
躁うつ病(双極性障害)は治りますか?
完全に治ることは難しいですが、適切な治療を受けることで症状をコントロールすることが可能です。
躁うつ病(双極性障害)で医療機関を受診すべき状態は?
極端な気分の変化、日常生活に支障をきたすような症状がありましたら、早めに受診していただくことを推奨します。
躁うつ病(双極性障害)の症状はどれくらい続きますか?
躁状態や抑うつ状態の持続期間は患者様により異なります。躁状態は数日から数週間、抑うつ状態は数週間から数ヶ月続くこともあります。
躁うつ病(双極性障害)の治療中に注意すべきことはありますか?
医師の指示に従い治療を継続することが重要です。また、症状の変化や薬の副作用などありましたら早めにご相談ください。