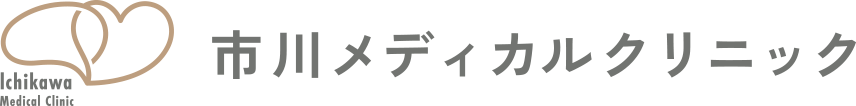- 初めて受診される方へ
- 再診の方へ
- 専門外来の方へ
- 診療の流れ
- 当院で対応可能な方
- 未成年者の診察(18歳未満)について
- 精神科・心療内科で利用できる制度について
- 院内での撮影・録画・録音について
- 費用について
初めて受診される方へ
初めて当院をご利用の方は、WEB予約もしくはLINE予約、お電話からのご予約をお願いいたします。予約状況によっては、当日の診察が可能な場合もありますが、当日受診をご希望の場合は、まずはお電話でお問い合わせください。
紹介状がなくても診察は可能ですが、スムーズで正確な診療を行うために、ご持参いただけると助かります。
また、お薬手帳をお持ちの場合は、必ずご持参ください。
初めて受診される際の持ち物
- 健康保険証(またはマイナンバーカード)
- 各種医療証(自立支援医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳、国民健康保険高齢受給者証など)
- お薬手帳(お持ちの場合。スマホアプリでも可)
- 紹介状(お持ちの場合のみ)
再診の方へ
再診の際も、WEB予約もしくはLINE予約、お電話からのご予約をお願いします。医師から指示された受診間隔がある場合は、その指示に従ってご予約ください。なお、前回の診察から6ヶ月以上経過している場合は、初診扱いとなりますのでご了承ください。
専門外来の方へ
当クリニックでは、以下の疾患に対して専門外来診療を行なっております。専門外来ご受診を希望される方は、お電話でのご予約をお願いします。
専門外来を希望される場合は、必ずお電話でご予約ください。
再診時の持ち物
- 健康保険証(またはマイナンバーカード)
- 各種医療証(自立支援医療受給者証、精神障害者保健福祉手帳、国民健康保険高齢受給者証など)
- お薬手帳(お持ちの場合。スマホアプリでも可)
診療の流れ
2来院・受付の流れ
ご来院の際は、まず受付を行ってください。その際に、健康保険証(もしくはマイナンバーカード)、各種医療証、紹介状(診療情報提供書)、お薬手帳をお持ちの方はご提示ください。
3診察
順番にお呼びしますので、番号が呼ばれましたら診察室にお入りください。診察後、必要に応じて心理検査などを実施することがあります。
診察時間の目安
初診はおよそ30分程度、再診は患者様の状態に応じて5〜15分程度となります。
当院は予約制ですが、他の患者様の状態によっては、予定の診察時間よりお待ちいただく場合もございます。ご了承ください。
4会計について
診察後はお会計をお願いいたします。処方がある場合は、処方箋をお渡ししますので、薬局にてお受け取りください。
当院で対応可能な方
未成年者の診察(18歳未満)について
当院では、18歳未満の未成年者の診療は専門外となっているため、ご相談内容によっては対応が出来ない場合がございます。ご予約の際には、この点にご留意ください。やむを得ない事情がある場合は、患者様ご自身での予約ではなく、保護者の方からお電話にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
精神科・心療内科で利用できる制度について
当院では、各種公的制度の申請にも対応しております。公的制度の利用には、医師による診断書が必要となる場合があります。詳細については、お住まいの自治体へお問い合わせください。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、精神的な障害を抱える患者様が定期的に通院し治療を受ける際の経済的負担を軽減するために設けられた公費負担医療制度です。精神保健福祉法および精神障害者総合支援法に基づき、各地方自治体が実施しています。制度を利用するには、お住まいの自治体で手続きが必要です。この制度を利用すると、原則として患者様の自己負担が1割に軽減され、健康保険の適用額との差額が支給されます。また、所得に応じて医療費の上限額が設定されており、患者様の負担がそれを超えることはありません。
自立支援医療制度の適用範囲
自立支援医療制度は、精神疾患に関連する通院医療に限って適用されます。指定医療機関での風邪や怪我の治療については、通常の健康保険の自己負担額を支払う必要があります。
自立支援医療制度の有効期限
有効期限は、自治体に受理された日から1年間です。毎年更新手続きが必要であり、更新の際には指定医療機関の医師による診断書が求められます。
自立支援医療制度の申請手続き
自立支援医療制度を利用するには、指定の医療機関で治療を受けていることが前提です。申請には、指定医療機関の医師による診断書が必要で、「重度かつ継続」に該当する場合は医師の意見書も提出する必要があります。
必要な書類が整ったら、お住まいの自治体の窓口で申請を行ってください。必要書類や窓口の詳細については、各自治体にお問い合わせください。
申請後、受給者証が届くまで数ヶ月かかることがあります。その間は、申請書の控えを受給者証の代わりとして使用できますので、大切に保管し、当院受診時にご持参ください。
受給者証が届いた後は、受診時に受給者証と自己負担限度額管理表をクリニックや薬局に提示してください。
自立支援医療制度の申請に必要なもの
- 医師による診断書
- 医師の意見書(「重度かつ継続」に該当する方)
- 世帯の所得を示す書類(課税証明書、非課税証明書など)
- 自立支援受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神的な障害により長期にわたって社会生活や日常生活に制約が生じている方が、社会的自立と参加を促進するために発行されます。障害の程度に応じて1~3級の3段階に分かれています。知的障害を持つ方は、福祉手帳と療育手帳を同時に申請することも可能です。
精神障害者保健福祉手帳の受給対象者
以下の条件を満たす方は、お住まいの地方自治体の窓口で申請することで手帳を受け取ることができます。
- 日常生活や社会生活に制約をもたらす精神疾患を長期間抱えていること
- 精神疾患の初診から6ヶ月以上が経過していること
精神障害者保健福祉手帳の有効期限
この手帳の有効期限は2年間です。更新手続きは、有効期限が切れる3ヶ月前から行うことができます。
精神障害者保健福祉手帳の申請手続き
精神保健福祉手帳を希望する場合は、まずかかりつけの医師に対象かどうかを確認してください。対象であれば、住民自治体の窓口で申請書や必要書類を取得します。
取得した書類を当院の外来受付に持参し、申請の可否を当院医師が判断します。申請書の記入には2週間から1ヶ月程度かかることがあるため、更新の場合は早めに申込むことをお勧めします。
必要書類が揃ったら、住民自治体窓口に提出してください。
申請から審査、交付まで数ヶ月かかるため、手帳が届くまでお待ちください。
精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの
- 医師による診断書
- 申請書
- 写真(約4cm×約3cm)
精神障害者年金制度
精神障害者年金制度は、精神的な障害やその他の病気、外傷によって働けない、または十分に働けない方を対象とした制度です。入院や通院中の方もこの制度の受給対象となる場合があるため、医師に相談することが重要です。
精神障害者年金制度の受給条件
- 厚生年金、国民年金、共済年金などの公的年金に加入しており、保険料納付期間中に精神障害の診断を受けたこと。
- うつ病、統合失調症、躁うつ病(双極性障害)などの指定された精神疾患を抱えていること。
- 保険料を3分の2以上納めていること。
なお、20歳になる前に精神疾患を発症した場合は、上記の条件に該当しなくても受給対象となります。
障害年金の種類
年金額は、初診時に加入していた年金の種類、障害の等級、扶養家族の有無によって異なります。
障害基礎年金(1~2級)
精神疾患の初診日に国民年金に加入していた方が対象で、障害等級が1級または2級に該当する場合、受給可能です。
障害厚生年金(1〜3級)
精神障害の初診日に厚生年金に加入していた方で、障害等級が1~3級に該当する場合が対象です。厚生年金は基礎年金に上乗せされる制度のため、1~2級に該当する方は障害基礎年金も同時に受給できます。
障害年金の申請手続き
障害年金の申請は、障害基礎年金と障害厚生年金で手続きが異なります。
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していなかった障害等級1級または2級の方は、自治体の窓口で申請できます。
国民年金に加入していた場合、初診日までに保険料の3分の2以上を納めていなければ障害基礎年金の受給はできません。条件を満たしている場合は、自治体窓口で申請可能です。
障害厚生年金
障害厚生年金や障害共済年金を受給するには、初診日までに保険料の3分の2以上を納付する必要があります。ただし、20歳未満で精神疾患を発症した場合はこの条件に該当しません。
障害厚生年金に加入している方で、条件を満たす場合は社会保険事務所に直接申請することが可能です。
申請には医師の診断書が必要です。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、生活費を補助するための制度です。働いている方やその家族の生活を守るために、一定の要件を満たした場合に支給されます。支給期間は最長1年6ヶ月で、支給金額は標準報酬月額の2/3を日割りした金額が、休業日数に応じて支給されます。この制度は組合健保、共済組合、全国健康保険協会の健康保険に加入している方が対象で、国民健康保険には適用されません。そのため、フリーランスや自営業の方は受給できない場合があります。申請書には「不詳」と記載されることがありますが、これは「過重労働」などと書かれて労災と見なされることを避けるためです。
傷病手当金を受給するための条件
傷病手当金を受け取るには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 健康保険に加入していること(被保険者であること)
- 医師から、業務外の病気やケガによる就業不能と診断されていること
- 雇用主から給与が支払われていないこと
- 連続して3日間の待機期間があること
退職後も傷病手当金は受け取れる?
退職後も一定の条件を満たしていれば、傷病手当金を受け取ることが可能です。具体的には、以下の基準をすべてクリアしている場合に限られます。
- 退職する前に1年以上継続して被保険者であったこと
- 退職時点で傷病手当金を受給しているか、受給資格があること
傷病手当金の支給期間
令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間は「支給開始日から1年6ヶ月」と定められました。例えば、1年間傷病手当金を受給した後に復職し、6ヶ月以上働いた場合、再び受給することはできません。この支給期間は1つの病気につき一度のみ適用され、同じ病名で再度の支給を受けることはできないため、注意が必要です。
傷病手当金の申請方法
企業では、総務や人事部門が申請手続きをサポートしていることが一般的です。必要書類を入手し、会社の記入が必要な部分を確認して、保険組合に申請します。小規模な企業では、この制度が知られていないこともあるため、直接健康保険組合に問い合わせることをお勧めします。
疾病手当金の申請に必要なもの
申請には、定められた書類が必要です。これらの書類は会社の総務や人事から入手可能で、申請書には事業主記入欄、従業員記入欄、主治医記入欄があります。当院に申請書を持参いただければ、主治医が診断内容を記入し、書類を発行いたします。申請後、支給の判断は健康保険組合が行いますが、必ずしも申請通りの金額が支給されるとは限りません。
診断書について
診断書とは、医師が患者様の病名や症状、治療内容、期間などを記載する公的な書類です。診断書の形式は医療機関によって異なる場合があり、企業や団体によっては特定の書式が求められることもあります。
診断書が必要な場面
診断書は、以下のような状況で必要とされることが多いです。
- 学校での休学
- 休職や復職
- 公的機関への手当や援助の申請
自賠責保険
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、道路交通法により全ての車両に加入が義務付けられている強制保険です。万が一、交通事故で他人を死傷させた場合に、加害者が負担する賠償金の一部を補うために設けられています。この保険は「人身事故」に対してのみ適用され、物損事故は対象外です。事故の被害者に対して最低限の補償を提供し、加害者の経済的負担を軽減するための制度です。自賠責保険の賠償限度額は、死亡事故で3,000万円、傷害事故で120万円、後遺障害の場合で最高4,000万円となっています。
自賠責保険の受給対象者
自賠責保険の対象となるのは、交通事故で負傷したり、亡くなった被害者およびその家族です。具体的には、歩行者や自転車に乗っている人、自動車に乗っている人、または二輪車の運転者や同乗者が事故に遭った場合が該当します。加害者側に重大な過失があっても、被害者が補償を受けられるのがこの保険の特徴です。自賠責保険は「対人賠償」のみをカバーするため、物損や車両の損害に対する補償は含まれません。
自賠責保険の申請手続き
自賠責保険の補償を受けるためには、事故後に適切な手続きを行う必要があります。まずは、加害者が保険会社に連絡し、事故の詳細を報告します。保険会社から必要な書類を受け取り、申請書に必要事項を記入します。申請には、交通事故証明書や医師の診断書、事故による損害を証明する書類などが必要です。事故の発生から申請までに時間がかかると、支給が遅れることがありますので、迅速な対応が求められます。保険会社が審査を行い、認定された損害額が被害者に支払われます。
自賠責保険の申請に必要なもの
自賠責保険の申請には、いくつかの書類が必要です。まず、「交通事故証明書」は必須で、事故が警察に届けられていることを証明する書類です。また、被害者が負傷している場合は「診断書」や「治療費の領収書」、後遺障害が残った場合は「後遺障害診断書」も必要となります。死亡事故の場合には、死亡診断書や埋葬費の領収書が必要です。これらの書類を保険会社に提出し、審査を経て支給が決定します。各書類は事故発生後、早めに準備し提出することが望ましいです。
後遺症認定の書類作成
交通事故によるけがの治療を行っても、完全に回復せず、後遺症が残る場合があります。そのような後遺症を補償してもらうためには、後遺症認定を受ける必要があります。後遺症認定は、自賠責保険や任意保険から適切な補償を受けるための重要な手続きであり、申請するには医師による「後遺障害診断書」の作成が必要です。この診断書は、残存する症状の種類や程度、日常生活への影響などを詳細に記載するもので、保険会社や損害賠償を求める際の重要な判断材料となります。
後遺症認定の流れ
後遺症認定の流れは、まず治療の継続が不可能と医師が判断する段階、つまり「症状固定」とされた時点で開始されます。症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態のことを指します。この状態に達したら、担当医に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。後遺障害診断書には、残存する症状やその影響、医学的な見解が詳細に記載されます。この診断書をもとに、保険会社が後遺障害等級を決定します。
後遺症認定の書類作成に必要なもの
後遺症認定の申請には、「後遺障害診断書」の他にいくつかの書類が必要です。まず、交通事故の発生を証明する「交通事故証明書」、過去の治療内容を示す「診療記録」や「治療費の領収書」も提出します。場合によっては、MRIやCTなどの画像診断結果も添付することが推奨されます。また、通院や治療が日常生活にどの程度影響を与えたかを示す書類も、認定の判断において役立つことがあります。
後遺症認定における重要なポイント
後遺症認定では、提出する書類の正確性と内容が重要です。特に「後遺障害診断書」には、具体的な症状の記載や日常生活への影響を詳細に記述することが求められます。これにより、後遺障害等級が適切に判断され、支払われる保険金の額が決まります。また、万が一認定結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことも可能です。その際には、追加の診断書や新たな証拠を提出する必要があります。
後遺症認定の際の注意点
後遺症認定を受ける際には、診断書の作成を依頼する医師選びも重要なポイントです。後遺障害に詳しい医師に依頼することで、より正確で説得力のある書類が作成される可能性が高まります。また、書類の内容が不十分だった場合、後遺障害等級が低く認定されるか、最悪の場合は認定されないこともあるため、書類を提出する前にしっかりと確認しておくことが重要です。時間が経つと詳細な記録が残りにくいため、早めの対応を心掛けることが求められます。
院内での撮影・録画・録音について
当院では、プライバシー保護および診療環境の安全確保のため、院内での撮影・録画・録音を一切禁止しております。診察中や待合室などでの撮影や録音は、他の患者様やスタッフの個人情報に触れる可能性があるため、ご遠慮いただいております。また、無断での撮影や録音が発覚した場合には、適切な対応を取らせていただくことがあります。診療に関する記録が必要な場合は、事前に医師やスタッフにご相談ください。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。