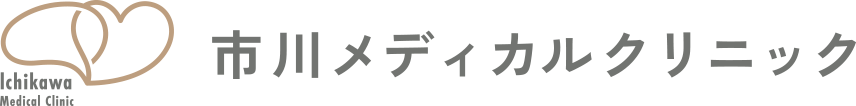睡眠障害とは
 睡眠障害は、十分な睡眠を得ることが出来ず、日常生活に支障をきたす状態を指します。主な睡眠障害には、不眠症、過眠症、睡眠時無呼吸症候群があります。不眠症は、寝つきが悪い、眠りが浅い、早朝に目が覚めるといった症状が特徴です。一方、過眠症は過度な眠気や突然の睡眠発作が主な症状となります。
睡眠障害は、十分な睡眠を得ることが出来ず、日常生活に支障をきたす状態を指します。主な睡眠障害には、不眠症、過眠症、睡眠時無呼吸症候群があります。不眠症は、寝つきが悪い、眠りが浅い、早朝に目が覚めるといった症状が特徴です。一方、過眠症は過度な眠気や突然の睡眠発作が主な症状となります。
睡眠障害の原因
心理的要因
ストレスや緊張
日常生活のストレスやプレッシャーが蓄積すると、交感神経が活性化し、リラックスできない状態が続きます。これにより、寝つきが悪くなったり、深い眠りが得られなくなったりします。職場の問題、人間関係、経済的な心配が主なストレスの原因となります。
うつ病・不安障害
うつ病の患者様は、寝つきが悪い、夜中に目が覚めてしまう、早朝に覚醒してしまうといった不眠の症状がよく見られます。また、不安障害の患者様は、心配事で脳が休まらず、寝つきが悪くなることが多いです。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
過去のトラウマやストレスフルな出来事を反復的に思い出し、夜に安心して眠れない場合があります。フラッシュバックや悪夢が原因で目が覚めることがあります。
身体的要因
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に気道が閉塞し、一時的に呼吸が止まる状態です。これにより、脳は酸素不足を感知し、断続的に目が覚めるため、深い眠りが得られません。いびきが強い人や肥満の人に多く見られます。
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
就寝中に脚に不快な感覚が生じ、じっとしていられずに脚を動かさずにはいられない状態になり、眠りが妨げられるようになります。
慢性痛
腰痛や関節痛、神経痛などの持続的な痛みがあると、痛みによって目が覚めたり、寝返りを打つたびに痛みを感じて深い眠りが妨げられることがあります。
その他
シフト勤務・夜勤
夜勤やシフト勤務をしている人は、体内時計(サーカディアンリズム)が乱れやすく、昼夜逆転の生活になることがあります。このリズムの乱れが、深夜や昼間の睡眠の質を低下させ、慢性的な不眠を引き起こします。
カフェイン・ニコチン・アルコール
カフェインやニコチンは覚醒作用があり、就寝前に摂取すると、寝つきが悪くなります。アルコールは一見眠りを促すように思われますが、実際には深い眠りを妨げ、夜間に目が覚めやすくなることがあります。
スマートフォン・テレビなど
寝る直前にスマートフォンやタブレット、テレビなどの画面を見ると、ブルーライトによってメラトニン(眠気を促すホルモン)の分泌が抑制され、入眠が遅れることがあります。
薬の副作用
一部の薬は睡眠に影響を与える可能性があります。例えば、抗うつ薬の一部は眠気を引き起こす一方、他の薬は不眠や夜間覚醒を引き起こすことがあります。また、ステロイドや降圧薬、気管支拡張薬なども睡眠を妨げることがあります。
薬物依存・アルコール依存
長期のアルコール依存や薬物乱用は、脳に変化を引き起こし、自然な睡眠パターンが崩れることがあります。アルコールや薬物を急にやめると、リバウンド現象で一時的に不眠が悪化することもあります。
加齢
加齢に伴い、深い眠り(徐波睡眠)が減り、夜中に目が覚めやすくなることがあります。また、加齢に伴うホルモンバランスの変化も睡眠に影響します。
睡眠障害の種類
不眠症
不眠症は、寝つきが悪い、夜中に目が覚めて再び眠れない、早朝に目が覚める、眠りが浅く十分に休めない状態が続く障害です。急性不眠(短期間)と慢性不眠(3ヶ月以上)があり、ストレス、心理的要因(うつ病、不安障害)、不規則な生活リズム、環境要因(騒音、光)が原因となります。これにより日中の疲労感や集中力の低下、イライラ感などが生じ、生活の質が大きく損なわれます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止、または著しく低下する状態が繰り返し起こる疾患です。特に「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」は、鼻から喉までの上気道が狭くなり、無呼吸や低呼吸が生じるタイプで、肥満や顎顔面形態、年齢、性別などがリスク因子となります。SASにより、深い睡眠が阻害され、日中の過度な眠気や疲労感、集中力低下、イライラ感などが引き起こされます。また、高血圧、心疾患、糖尿病、脳血管疾患といった生活習慣病のリスクを高めることもわかっています。
過眠症
過眠症は、日中に強い眠気が生じ、通常の睡眠時間を確保しても過度の眠気や突然の睡眠発作が起こる状態です。ナルコレプシーが代表的な過眠症で、神経伝達物質の異常が原因とされています。症状には、昼間の異常な眠気に加え、カタプレキシー(感情の変化で筋力が急に低下する発作)や睡眠麻痺(金縛り)、幻覚などが伴うことがあります。治療には、覚醒剤や抗うつ薬を使用し、日中の眠気を軽減します。
概日リズム睡眠障害
概日リズム睡眠障害は、体内時計(サーカディアンリズム)が乱れることにより、通常の就寝時間や起床時間に合わない状態です。夜更かしや不規則な生活、時差ぼけ、シフト勤務などが原因で、寝たい時間に眠れず、朝起きられない、昼間に眠気が強いといった症状が出ます。体内時計を整えるための光療法や、メラトニン補充療法が治療法として使われます。規則的な生活リズムの確立が改善の鍵となります。
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
むずむず脚症候群は、就寝時や安静時に脚に不快な感覚(むずむず、ピリピリ、ズキズキなど)が生じ、脚を動かさないとその不快感が和らがない状態です。症状がひどい場合は、寝つきが悪くなり、眠りの質が低下します。原因ははっきりしていませんが、鉄分の不足や神経系の異常、遺伝が関与していると考えられています。治療法には鉄分の補給やドーパミン作動薬の使用、ライフスタイルの改善が含まれます。
周期性四肢運動障害(PLMD)
周期性四肢運動障害は、睡眠中に脚や腕が繰り返し無意識に動く障害です。主に脚が定期的にピクッと跳ねるような動きを示し、これにより眠りが断続的になります。本人は自覚していないことが多く、日中に強い眠気や疲労感が現れることがあります。原因は神経系の異常で、特に高齢者に多いです。治療法にはドーパミン作動薬や抗けいれん薬のほか、カフェインやアルコールを避けることも症状の軽減に役立ちます。
レム睡眠行動障害
レム睡眠行動障害は、レム睡眠中に身体が動いてしまう障害です。通常はレム睡眠中に筋肉が弛緩して夢を見ても体が動かないように保たれますが、この障害では夢の内容に合わせて激しく動いたり、叫んだりします。これはパーキンソン病や認知症など神経変性疾患の前兆として現れることもあり、早期診断が重要です。治療にはクロナゼパムやメラトニンが使用され、また安全な睡眠環境を整えることが推奨されます。
睡眠時遊行症(パラソムニア)
睡眠時遊行症は、睡眠中に異常な行動や体験が生じる障害です。寝ぼけ、夜驚症(子供に多く、突然叫び出して目が覚める)、悪夢、睡眠麻痺(金縛り)などが含まれます。原因は脳が睡眠と覚醒の間で不安定な状態にあることです。特に疲労、ストレス、アルコール摂取が引き金となることが多いです。
短眠症(ショートスリーパー)
短眠症は、一般的な成人の平均睡眠時間(7〜8時間)よりもはるかに短い睡眠で十分な休息が得られる状態です。これ自体は病的なものではなく、遺伝的に短い睡眠時間で健康を維持できる人が対象です。問題として認識されることは少ないですが、無理に一般的な睡眠時間を確保しようとすることで逆にストレスや不眠が生じることがあります。基本的には特別な治療を必要としませんが、生活リズムが大きく崩れる場合は調整が必要です。
睡眠障害の症状
- 寝つきが悪い(入眠困難)
- 夜中に何度も目が覚める(中途覚醒)
- 早朝に目が覚めてしまう(早朝覚醒)
- 深く眠れない、眠りが浅い
- 日中の強い眠気
- 集中力や注意力の低下
- 疲労感が取れない
- いびきがひどく、呼吸が止まる(無呼吸)
- 脚や腕がむずむずして眠れない(むずむず脚症候群)
- 寝ている間に異常な動きや行動をする(レム睡眠行動障害など)
- 金縛りにかかる(睡眠麻痺)
- 悪夢を頻繁に見る
など
睡眠障害に
なりやすい人(傾向)
 睡眠障害になりやすい人(傾向)として、ストレスを抱えやすい人、不規則な生活リズムを送っている人が挙げられます。特に、シフト制や夜勤に従事する人は、体内時計が乱れやすく睡眠障害を発症しやすいです。また、うつ病や不安障害など精神疾患を持つ人や高齢者もリスクが高くなります。さらに、過度なカフェイン、アルコール摂取も睡眠の質を低下させ、睡眠障害を引き起こす原因となります。
睡眠障害になりやすい人(傾向)として、ストレスを抱えやすい人、不規則な生活リズムを送っている人が挙げられます。特に、シフト制や夜勤に従事する人は、体内時計が乱れやすく睡眠障害を発症しやすいです。また、うつ病や不安障害など精神疾患を持つ人や高齢者もリスクが高くなります。さらに、過度なカフェイン、アルコール摂取も睡眠の質を低下させ、睡眠障害を引き起こす原因となります。
睡眠障害の検査・診断方法
睡眠障害の検査・診断は、医師による問診と診察に基づき行います。必要に応じて睡眠パターンを記録する睡眠日誌や、睡眠の質を評価するポリグラフ検査を行います。ポリグラフ検査などが必要な場合、連携する医療機関をご紹介いたします。
睡眠障害の治療方法
薬物療法
必要に応じて、睡眠障害には薬物療法を行います。例えば、不眠症には睡眠薬(ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系)を短期間使用します。また、睡眠時無呼吸症候群には、呼吸をサポートする薬やうっ血除去薬を処方することもあります。過眠症やレム睡眠行動障害には、覚醒剤や抗うつ薬が使われる場合もあります。薬物療法は、短期間の使用が基本で、根本的な改善に向けた他の療法と併用することが多いです。
心理療法(認知行動療法)
不眠症に対しては、不適切な睡眠に関する考え方や行動を修正するために認知行動療法を行うことがあります。
生活習慣の改善
まず、睡眠環境や生活習慣を整えることが重要です。これには、毎日同じ時間に就寝・起床する、寝る前にカフェインやアルコールを避ける、電子機器の使用を控える、寝室を快適に保つ(暗く、静かに、適温にする)などが含まれます。これらの睡眠衛生の改善は、不眠症や概日リズム睡眠障害などに有効です。
睡眠障害に関するよくある質問
睡眠障害は治りますか?
多くの睡眠障害は、適切な治療や生活習慣を見直すことで改善可能です。
寝ても疲れが取れないのは睡眠障害ですか?
日常的に十分な時間寝ても疲れが取れない場合、睡眠時無呼吸症候群や不眠症など、何らかの睡眠障害が関係している可能性があります。
昼間(日中)に強い眠気があるのは、睡眠障害ですか?
日中の強い眠気は、過眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害が原因のこともあります。特に、十分な睡眠を取っているにも関わらず、日中居眠りをしてしまうほどの強い眠気がありましたらお早めにご相談ください。
睡眠障害は遺伝しますか?
睡眠障害の一部は、遺伝的要因が関与しているとされます。家族に睡眠障害の罹患者がいる場合、リスクが高まりますので、特に生活習慣などに注意しましょう。
どれくらいの睡眠時間が必要ですか?
成人の場合、一般的に7~9時間程度の睡眠をとることが推奨されています。ただし、個人差がありますので、自分に合った睡眠時間を見つけられるようにしましょう。
ストレスが睡眠に与えることもありますか?
ストレスは睡眠の質を低下させ、不眠症の原因なり得ます。ストレスをゼロにすることは難しいので、上手くストレスを付き合えるようにしましょう。
夜勤の仕事をしている場合、どのようにしたら良い睡眠がとれますか?
夜勤の仕事をされている場合、シフトの前後で睡眠時間を工夫する必要があります。その際、睡眠環境が重要になりますので、暗い環境で、静かな状態を作れるようにしましょう。