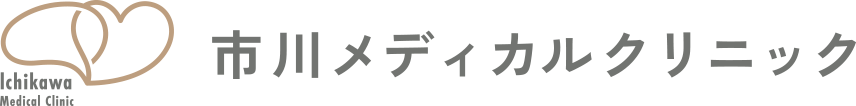- 心理検査
- 発達障害に関する検査
- 認知機能検査
- 睡眠検査(必要な場合連携医療機関をご紹介いたします)
- 脳波検査(必要な場合連携医療機関をご紹介いたします)
- 血液検査
- 画像検査(必要な場合連携医療機関をご紹介いたします)
心理検査
ロールシャッハテスト
ロールシャッハテストは、投影法に基づく心理検査の一つで、患者様にインクのしみを見せ、その印象や解釈を言葉で表現していただくものになります。患者様の無意識の思考や感情、対人関係のスタイルを評価するために使用されます。主に人格の特性や情緒的な問題を把握するために用いられ、特に精神病理の検出に効果的です。
MMPI(ミネソタ多面的人格目録)
MMPIは、心理的な健康や人格特性を評価するための自己報告式の質問票です。550以上の質問から成り、さまざまな心理的な側面を網羅しています。うつ病、不安、ストレス、自己評価など、多くの心理的問題のスクリーニングに使用されます。結果は、特定の心理的な問題の有無やその程度を把握し、治療方針を決定するために役立たせます。
BDI(ベックうつ病評価尺度)
BDIは、うつ病の症状を評価するために使用される自己報告式の質問票です。21項目から構成されており、各項目はうつ病のさまざまな側面を反映しています。回答は0から3のスケールで行い、総得点に基づいてうつ病の重症度が評価されます。この検査は、うつ病の初期診断だけでなく、治療効果のモニタリングにも利用されます。
HADS(病院不安うつ尺度)
HADSは、不安と抑うつの評価を目的としたスケールです。14項目から成り、うつと不安の2つのサブスケールがそれぞれ7項目ずつあります。各項目に対して4段階の回答を行い、得点によって不安や抑うつの程度を評価します。特に身体的な病気を抱える患者様において、心理的な苦痛を評価し、適切な治療や支援を行うために重要な検査となります。
POMS(気分状態プロフィール)
POMSは、特定の時間における気分や感情状態を評価するための自己報告式の質問票です。65項目から成り、緊張、不安、抑うつ、活力、疲労などの複数の気分の側面を測定します。気分状態の変化を把握するため、心理的な状態を評価するのに適しています。特に心理療法や精神的な健康管理において、患者様の気分の変化を追跡するために用いられます。
CES-D(うつ病自己評価尺度)
CES-D(The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale)は、うつ病の症状を自己評価するための尺度で、1971年にアメリカ国立精神衛生研究所(NIMH)により開発されました。20項目からなり、各質問に「ほとんどなかった」から「ほとんどいつもあった」までの4段階で回答します。気分の落ち込みや不眠、食欲の変化など、過去1週間の症状の頻度を測ることで、うつ病の傾向を把握することが目的です。得点が高いほど、うつ状態の可能性が示唆されますが、正式な診断ではなく、精神科専門医の診察が必要です。日本でも、臨床や研究で広く活用されています。
発達障害に関する検査
WAIS(ウェイス成人知能検査)
WAISは成人向けの知能検査で、言語性知能と動作性知能を評価するための様々な課題が含まれています。言語理解、知覚推理、作業記憶、処理速度などの認知能力を測定します。結果は、高次脳機能障害、器質性疾患の影響、発達障害や学習障害の診断に利用します。
AQ(自閉スペクトラム指数)
AQは、自閉スペクトラム症(ASD)の特性を評価するために設計された自己報告式の質問票です。50項目から構成され、社会的相互作用、コミュニケーション、想像力、注意の集中など、ASDに関連するさまざまな特性を評価します。得点が高いほど、自閉スペクトラム症の傾向が強いことを示します。診断補助として、また支援の必要性を評価するために利用されます。
ADOS(自閉症診断観察尺度)
ADOSは、自閉症スペクトラム障害を診断するための構造化された観察評価です。4つの構成からなり、年齢や言語能力に応じて適切な構成を選択します。社会的相互作用やコミュニケーション、遊びや創造的な表現の仕方を観察し、自閉症の診断を行う上での重要な検査です。
バウムテスト
バウムテストは、人物や出来事に対する無意識の感情や思考を探るために、木を描いていただく検査です。描かれた木の形や大きさなどが患者様の心理的特性や感情状態を示すとされています。特に発達障害や情緒的問題の評価に利用され、患者様の内面的な状態を理解する手助けとなります。
MSPA(発達障害の特性別評価法)
MSPA(Monochrome Standardized Progressive Matrices for ASD)は、発達障害の特性を把握するための評価法で、日本で開発されました。主に自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)などの発達特性を持つ子どもを対象に、認知特性や問題解決能力、社会性の特徴を多角的に評価することを目的としています。標準化されたモノクロの図形を用い、特性別に視覚的推論や注意力を測ることで、個々の強みや弱みを把握します。評価結果は、個別の指導・支援計画に役立てられるほか、保護者や教育機関と共有し、適切な支援に繋げます。
認知機能検査
MMSE(簡易認知機能検査)
MMSEは、認知機能の基本的な評価を行うための簡便なスクリーニング検査です。質問項目は、時間や場所の認識、記憶力、注意力、言語能力など多岐にわたり、合計30点満点で評価されます。高齢者の認知症や他の神経認知障害の早期発見に特に効果的であり、簡単に実施できるため、幅広い医療現場で利用されています。
FAB(前頭葉機能検査)
FABは、前頭葉の機能を評価するための検査です。前頭葉に障害がある場合、判断力、計画力、注意力が低下することがあります。FABは、5つの課題を通じて、これらの認知機能を測定し、認知症や他の神経疾患との鑑別を行います。
MoCA(モントリオール認知機能検査)
MoCAは、軽度認知障害(MCI)の評価を目的とした検査で、視覚的な認知、記憶、言語、注意など多様な側面を測定します。検査は約10分程度で実施でき、30点満点で評価されます。MCIの早期発見に特に有用であり、認知機能の変化を定期的に追跡するためにも使用されます。
CDR(Clinical Dementia Rating)
CDR(Clinical Dementia Rating)は、認知症の進行度を評価するための尺度で、0から3までの5段階で判定します。評価項目には記憶、見当識、判断力・問題解決能力、社会的役割、家庭生活・趣味、自己管理の6つの分野があり、主に患者様本人やその家族への面接を通して評価を行います。各分野の得点を総合して、0は「正常」、0.5は「疑い」、1は「軽度」、2は「中等度」、3は「重度」と診断し、認知症の早期発見と進行度の把握に役立てられます。簡便で信頼性が高いため、広く用いられている検査です。
ADAS(アルツハイマー病評価尺度)
主にアルツハイマー型認知症の重症度を評価するために使用される評価尺度です。記憶や見当識、言語機能、構成能力など複数の認知機能を測定し、全体的なスコアで認知症の進行状況を把握します。軽度から重度までの幅広い症状に対応しており、治療効果の評価にも有用です。
WMS-R(ウィスクラー記憶検査)
記憶能力を評価する検査で、特に高齢者の認知機能障害の診断に活用されます。短期記憶や長期記憶、視覚と聴覚を介した記憶を測定し、個別の能力や全体的な記憶力を評価します。脳損傷や認知症の進行評価に役立ちます。
標準失語症検査(SLTA)
失語症の診断に使用される検査で、言語機能のさまざまな側面(発話、理解、復唱、読み、書き)を総合的に評価します。失語症のタイプや重症度を診断し、治療方針を決定する上での基礎的な情報を得られます。
標準注意検査法・標準意欲評価法
注意や意欲といった心理的特性を客観的に評価するための検査法です。集中力や持続力、注意力の分散度合い、意欲の程度などを数値化し、注意障害や意欲低下が関係する精神疾患の診断や評価に役立ちます。
WCST(ウィスコンシン・カード分類検査)
遂行機能を評価するための検査で、カードを分類しながらルールの変更に柔軟に適応できるかを測定します。前頭葉機能の評価に有用で、認知症や統合失調症などの患者様の柔軟性や問題解決能力を評価します。
SCID(構造化面接法)
DSM診断基準に基づく構造化された面接法で、精神疾患の診断を行います。質問が系統立てられており、再現性が高く、臨床現場で広く利用されています。診断の一貫性や信頼性を保つことができ、研究や診療の標準化に役立ちます。
BADS(遂行機能障害症候群の行動評価)
日常生活での遂行機能障害を評価する検査です。計画・判断・自己モニタリングなどの能力を測定し、日常生活での問題解決能力や計画性がどの程度機能しているかを評価します。前頭葉機能障害の有無や重症度を判断します。
ROCFT(レイの複雑図形検査)
視覚記憶や視空間認知、遂行機能を評価する検査で、提示された複雑な図形を再現することでこれらの認知機能を測定します。認知症や脳損傷の患者様の記憶や構成能力を評価するのに有効です。
NPI(Neuropsychiatric Inventory)
認知症患者様に見られる精神症状や行動障害を評価するための質問票です。興奮や抑うつ、幻覚、興奮などの多様な症状について評価し、介護者への負担軽減のための介入方法を検討する際に活用されます。
睡眠検査(必要な場合連携医療機関をご紹介いたします)
PSG(ポリソムノグラフィー)
PSGは、睡眠の質や障害を評価するために、睡眠中の脳波、呼吸、心拍数、血中酸素濃度などを同時に記録する検査です。睡眠時無呼吸症候群や不眠症などの睡眠障害の診断に役立ちます。
脳波検査(必要な場合連携医療機関をご紹介いたします)
EEG(脳波測定)
EEGは、脳の電気活動を測定するための検査で、脳波の変化を観察します。特にてんかんやその他の神経障害の診断に重要です。電極を頭皮に配置し、脳波をリアルタイムで記録します。
血液検査
ホルモン検査(甲状腺機能、ストレスホルモンなど)
ホルモン検査は、甲状腺機能やストレスホルモン(コルチゾールなど)の測定を行います。甲状腺機能の異常は、うつ病や不安症状に影響を及ぼすことがあり、ホルモンバランスの評価は重要です。
ビタミン・ミネラル不足の評価
ビタミンやミネラルの不足は、認知機能や精神状態に影響を与えることがあります。血液検査を通じて、特にビタミンB12、ビタミンD、鉄分などの欠乏がないかを評価します。不足が見られた場合は、適切な栄養補助や食事指導が行うことがあります。
炎症マーカー、糖尿病や脂質異常などの全身状態の確認
炎症マーカーや血糖値、脂質レベルの測定は、全身の健康状態を評価するために行われます。特に慢性的な炎症は、精神的な健康にも影響を与えることが知られており、早期の発見が重要です。
画像検査(必要な場合連携医療機関をご紹介いたします)
頭部MRI検査
MRIは、磁気共鳴画像法を用いて脳や体内の構造を高精度で撮影する検査です。脳腫瘍、脳梗塞、出血などの異常を検出するために広く利用されます。特に、詳細な画像が得られるため、微細な病変の診断に優れています。検査は非侵襲的で、放射線を使用しないため、安全性が高いとされています。下記の場合はMRIを実施することができない場合があります。
- 体内に磁性を持つ医療機器や金属がある場合
- ペースメーカーや除細動器(一部MRI対応機器を除く)。
- 神経刺激装置(一部対応機器を除く)。
- 人工内耳や埋め込み型聴覚補助デバイス。
- 体内金属片(特に磁性の強い金属:鉄やコバルトなど)。
- 血管クリップ(特に脳動脈瘤の治療に用いるものが非対応の場合)。
- 一部の人工関節や整形外科用金属プレート。
頭部CT検査
CTは、コンピュータ断層撮影を用いて体内の断面画像を得る検査で、特に脳の急性の異常(脳出血、脳梗塞など)の診断に役立ちます。迅速に画像を取得できるため、緊急時の診断に適しています。X線を使用しており、放射線被ばくが伴うため、必要な場合に限って行われます。
PET検査
PETは様々な病態分子に結合する放射性薬剤を投与し、その分布を特殊なPETスキャナーで捉えて画像化する核医学検査の一種です。PETにより、脳内の神経伝達物質の機能、脳内に蓄積する異常タンパク質、脳の代謝や血流などを評価することができます。アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβの脳内沈着を確認するのが、アミロイドPET検査です。認知症の約半数がアルツハイマー病によるものとされています。アルツハイマー病では、脳内にアミロイドβやタンパク質が沈着し、これが神経細胞に障害を与え、認知機能が低下すると考えられています。
アミロイドβは認知症を発症する前から脳内に沈着すると考えられ、アミロイドPET検査はこの沈着を確認できる検査となります。また、近年開発されたタウPETにより脳内に蓄積するタウ蛋白質を高精度に検出可能であることが示されています。しかしながら現在ではこれらアミロイドPET、タウPETを行える施設は国内でもかなり限られています。当院では、PET検査が必要な方やPET検査を含む臨床研究にご参加頂ける方は、連携医療機関および連携研究機関に紹介することが可能な場合もございますので、お問い合わせください。